Nostalgie du Futur “Harmonia”
未来のノスタルジー “ハルモニア”
福井 真菜
文化・時代・世界の“調和”を実験的録音で捉えた
《未来のノスタルジー》新章
「未来のノスタルジー」シリーズの新章となる二部作 “ハルモニア” は、「調和」をテーマに、異なる世界を結びつける試みです。
前作「未来のノスタルジー “ジャポニスム”」の三部作では、19〜20世紀の日本とフランス、東洋と西洋の交錯する文化を、ドビュッシー、ラヴェル、武満徹らの作品を通して紡ぎ出しました。
本作「未来のノスタルジー “ハルモニア”」二部作では、まず「未来のノスタルジー ハルモニア I」においてムソルグスキーが絵画から受けた印象を音楽に昇華した「組曲 展覧会の絵」を全曲ピアノソロで収録。19世紀末から20世紀初頭のロシアに息づく民族性、西洋と東洋の交差点で生まれる音楽的“調和”、そして絵画と音楽という異なる表現の“調和”を描き出します。
続く 「未来のノスタルジー ハルモニア II」では、ライヒ「シックス・ピアノズ」、ラフマニノフ「ヴォカリーズ」、モーツァルト「アヴェ・ヴェルム・コルプス」(リスト編曲)を収録。なかでも「シックス・ピアノズ」では、6台のピアノを円形に配置し、一人のピアニストが多重録音によって重層的な響きを構築。聞き手は円の中心に立つかのように、秩序と揺らぎ、能動と受動といった相反する要素が呼応し合う動的な“調和”を体感します。
この「未来のノスタルジー “ハルモニア”」二部作は、表裏・対立・距離・融合といった関係性の境界をあいまいにしながら、異なる様式・時代・思想を響き合わせ、新たなハーモニーの可能性を探る旅へと誘います。
《未来のノスタルジー》は、シリーズを通して、19世紀末に西洋で広まったジャポニスムと、その時代に前衛的な役割を果たした作曲家、そしてその影響を受けた作曲家たちの作品を通して、時代と芸術の交差を描き出しています。
「未来のノスタルジー “ジャポニスム”」Vol.1《ジャポニスム》、Vol.2《オリエントと日本》 Vol.3《珠玉の小品》に続き、新章として本作「未来のノスタルジー “ハルモニア”」Vol.4《ハルモニア I》、Vol.5《ハルモニア II》へと展開していきます。
前シリーズ「未来のノスタルジー“ジャポニスム”」は、ドビュッシー、スクリャービン、シマノフスキをはじめとする〈ジャポニスム〉の影響を受けた作曲家たち、そしてドビュッシーやメシアンらフランス音楽の系譜を色濃く感じさせる武満徹の楽曲を収録。 〈ジャポニスム〉を主題に、フランス音楽、オリエント、そして東洋と西洋の交錯を内包した、珠玉の作品集です。
「未来のノスタルジー “ジャポニスム”」から「未来のノスタルジー “ハルモニア”」へ、五つの作品を通して紡がれる文化と時代の交差をお楽しみください。



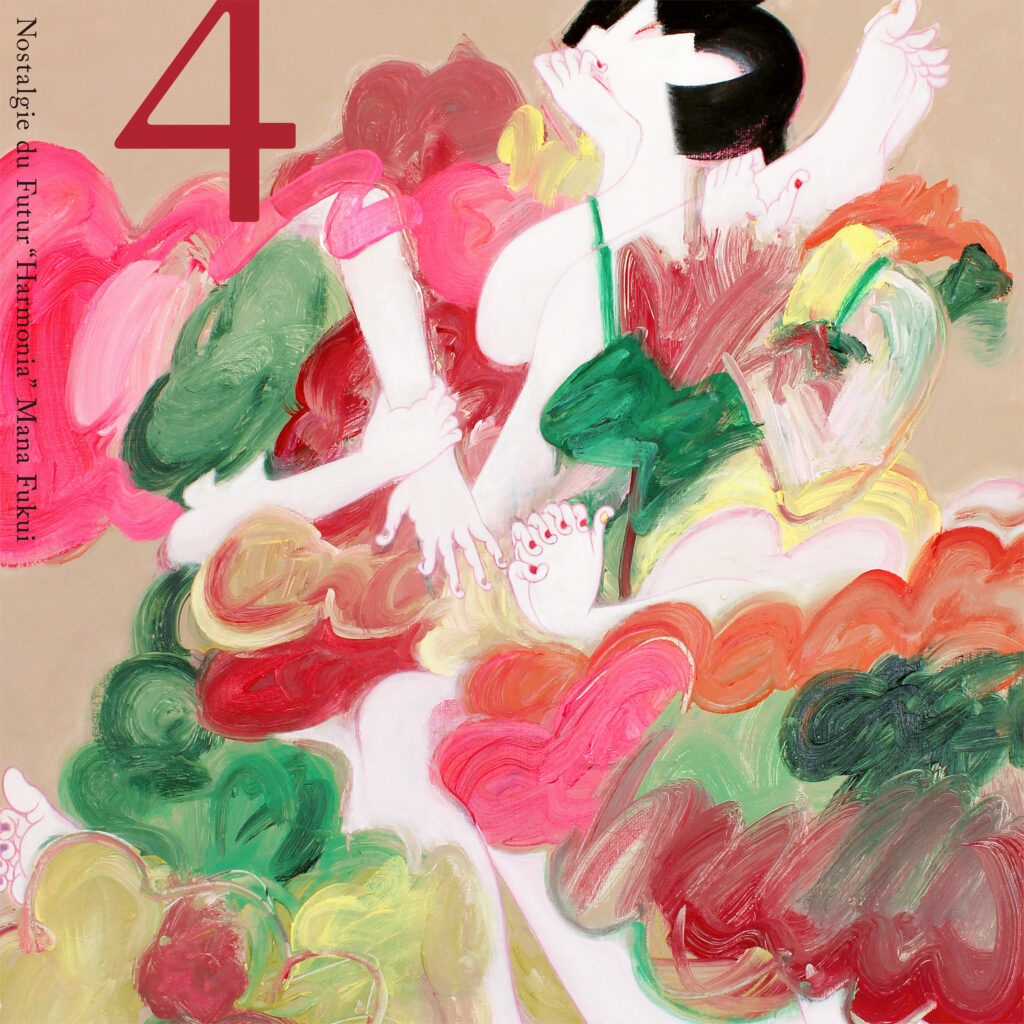
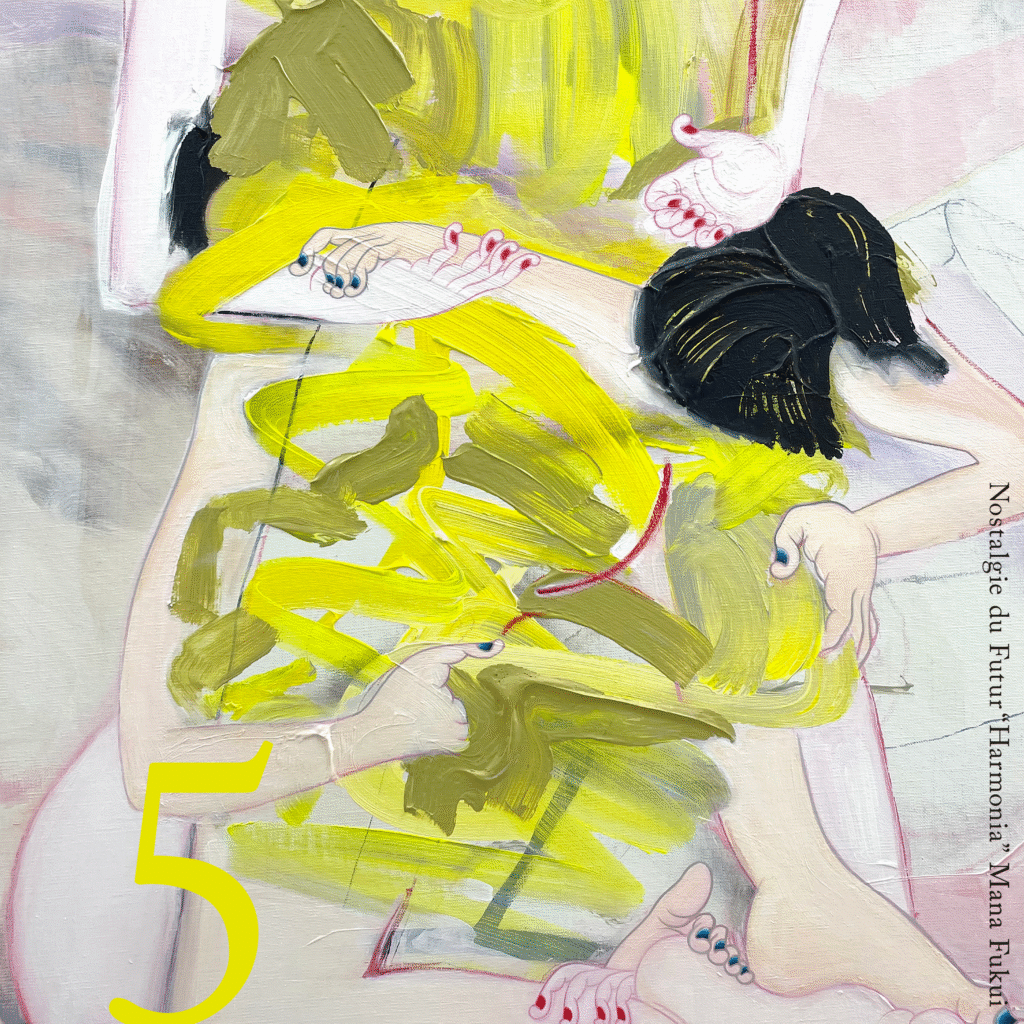
「未来のノスタルジー“ジャポニスム”」
福井真菜による《未来のノスタルジー》シリーズは、Vol.1〜Vol.3の「未来のノスタルジー“ジャポニスム”」三部作と、「未来のノスタルジー “ハルモニア”」二部作の、5つの作品で構成されています。
「未来のノスタルジー“ジャポニスム”」は、時代ドビュッシー、スクリャービン、シマノフスキをはじめとする〈ジャポニスム〉の影響を受けた作曲家たち、そしてドビュッシーやメシアンらフランス音楽の系譜を色濃く感じさせる武満徹の楽曲を収録。 「ジャポニスム」を主題に、フランス音楽、オリエント、そして東洋と西洋の交錯を内包した、珠玉の作品集です。
「未来のノスタルジー “ハルモニア”」と合わせてお聴きください。
古代ギリシャにおいて芸術を司る9人の女神たちを、人々はムーサ(Μοῦσαι)と呼びました。
彼女たちは全能の神ゼウスと「記憶」の女神ムネモシュネーの間に生まれた9人の姉妹で、舞踊、音楽、演劇、詩、天文学などを象徴しています。
記憶の女神から芸術が生まれるということは、芸術とは人々が受け継いだ記憶とその叡智の上に成り立っているという事実、また、9人の姉妹の存在は音楽や舞踊など、各分野の間の関連性の重要さを示唆しています。
人類は、その歴史において各分野の知の極地を追い求めてきました。それはその専門領域の探究の道を極め、造詣を深める反面、それぞれの分野の交流を狭める弊害も発生しました。
いま、文化・芸術・学問の多岐に渡る幅広い視点での往来の大切さとその相乗効果を見つめ直す時代となりました。それは各分野の断絶の終わりであり、それぞれの知と文化の融合によるシナジー効果を生み出すことでしょう。
友人の画家の遺作絵画よりインスピレーションを得て作曲されたムソルグスキーの「組曲 展覧会の絵」。そして、万物の理を哲学的、数学的かつ音楽として表現したライヒの「シックス・ピアノズ」。
先人たちから脈々と受け継がれてきた叡智が凝縮されたこれらの作品には、人間こそがたどり着ける芸術の高みを感じさせます。AIの構造化されたデータベースによるものではない、人間の多層的で多脈な芸術へのアプローチをこれからの世代へ受け渡すために、現代の私たちからの問題提起として、調和をテーマとしたアルバム「ハルモニア」を発表させていただきます。
福井 真菜(ピアニスト、本作品キュレーション)
Nostalgie du Futur “Harmonia”
– 未来のノスタルジー“ハルモニア” –
福井真菜
収録日・場所:2024年1月11日〜14日、5月16日〜19日 八ヶ岳やまびこホール
本作品は、Dolby Atmos版およびステレオ版を各種音楽サブスクリプション・サービスよりお楽しみいただけます。
※ご試聴いただける各種音楽サブスクリプション・サービスは、配信ディストリビューターの都合により変更になる場合がございます。
Vol.4
未来のノスタルジー ハルモニア I
Nostalgia of the Future – Harmonia I
Vol.4《ハルモニア I》では、ムソルグスキーの《組曲 展覧会の絵》全曲をピアノソロで演奏しています。
「組曲 展覧会の絵」は、ジャポニスムがヨーロッパを席巻していた同時期にロシアの作曲家、ムソルグスキーによって作曲されました。
ムソルグスキーの作品に見られる独自の表現は、西洋的な和声学や音楽学の枠組みでは捉えきれません。それは、西洋と東洋の狭間に位置するロシアという土壌から生まれたものだと気づかされます。
「展覧会の絵」は、絵画から受けた印象を音楽に表現した作品であり、広大な大地を思わせる土着的な力強さと、荘厳さを兼ね備えた傑作です。東洋と西洋、絵画と音楽など、異なる世界の範疇を凌駕し、その融合による壮大な拡がりは平和への祈りとも言えることでしょう。
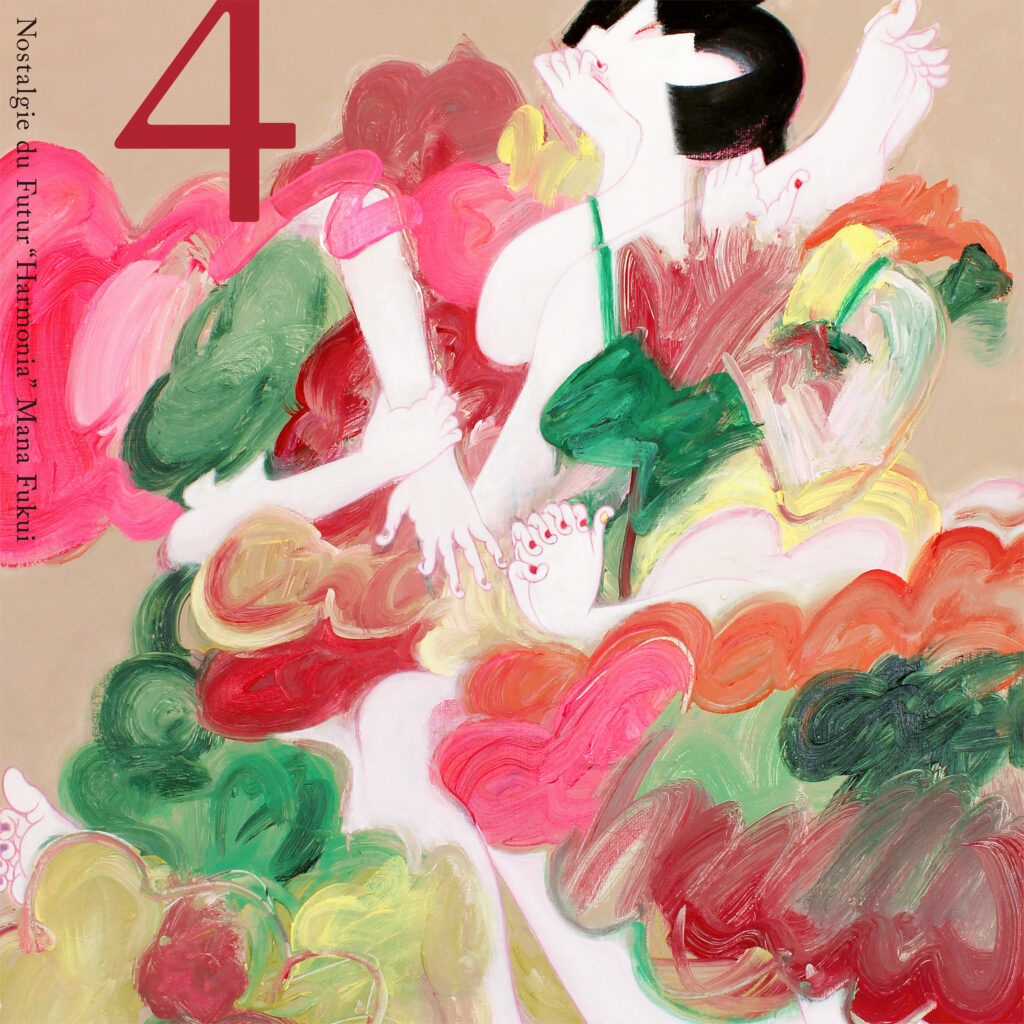
Track List
| 1 | 組曲「展覧会の絵」プロムナード I | モデスト・ムソルグスキー |
| 2 | 組曲「展覧会の絵」No.1 小人 | モデスト・ムソルグスキー |
| 3 | 組曲「展覧会の絵」プロムナード II | モデスト・ムソルグスキー |
| 4 | 組曲「展覧会の絵」No.2 古城 | モデスト・ムソルグスキー |
| 5 | 組曲「展覧会の絵」プロムナード III | モデスト・ムソルグスキー |
| 6 | 組曲「展覧会の絵」No.3 チュイルリーの庭 遊んだ後の子供たちの喧嘩 | モデスト・ムソルグスキー |
| 7 | 組曲「展覧会の絵」No.4 ビドロ(牛車) | モデスト・ムソルグスキー |
| 8 | 組曲「展覧会の絵」プロムナード IV | モデスト・ムソルグスキー |
| 9 | 組曲「展覧会の絵」No.5 卵の殻をつけた雛鳥のバレエ | モデスト・ムソルグスキー |
| 10 | 組曲「展覧会の絵」No.6 ザムエル・ゴルデンベルクとシュムイレ | モデスト・ムソルグスキー |
| 11 | 組曲「展覧会の絵」プロムナード V | モデスト・ムソルグスキー |
| 12 | 組曲「展覧会の絵」No.7 リモージュの市場 | モデスト・ムソルグスキー |
| 13 | 組曲「展覧会の絵」No.8 カタコンブ ー 死せる言葉による死者への話しかけ | モデスト・ムソルグスキー |
| 14 | 組曲「展覧会の絵」No.9 鶏の脚の上に建っている小屋(バーバ・ヤーガ) | モデスト・ムソルグスキー |
| 15 | 組曲「展覧会の絵」No.10 キエフの大きな門 | モデスト・ムソルグスキー |
Vol.5
未来のノスタルジー ハルモニア II
Nostalgia of the Future – Harmonia II
Vol.5《ハルモニア II》では、スティーブ・ライヒ「シックス・ピアノズ」、ラフマニノフ「ヴォカリーズ」、リスト編曲によるモーツァルト「アヴェ・ヴェルム・コルプス」を収録しています。
中でも「シックス・ピアノズ」では、6台のピアノを円形に配置し、一人のピアニストが多重録音によって重層的な響きを作り出しています。緻密なシンクロと微細な揺らぎが生み出す音像は、対立するものが調和し、ひとつの世界を形づくる瞬間を鮮烈に体験させてくれます。それはあたかも自己消滅による空間との一体感とも言える不思議な感覚であり、特に空間オーディオでのリスニングでは、聴き手が円の中心に立つかのような感覚を味わい、音に包み込まれる没入的な体験が可能となります。
「ヴォカリーズ」は、大地や自然の息吹、人間の営みを感じさせる作品。対して「アヴェ・ヴェルム・コルプス」は、宗教的な精神性の純粋さを湛え、透明で崇高な響きを放ちます。両者の対比によって「地」と「天」の世界が呼応し合い、アルバム全体が「ハルモニア(調和)」の名にふさわしい一つの統合された世界観を提示しています。
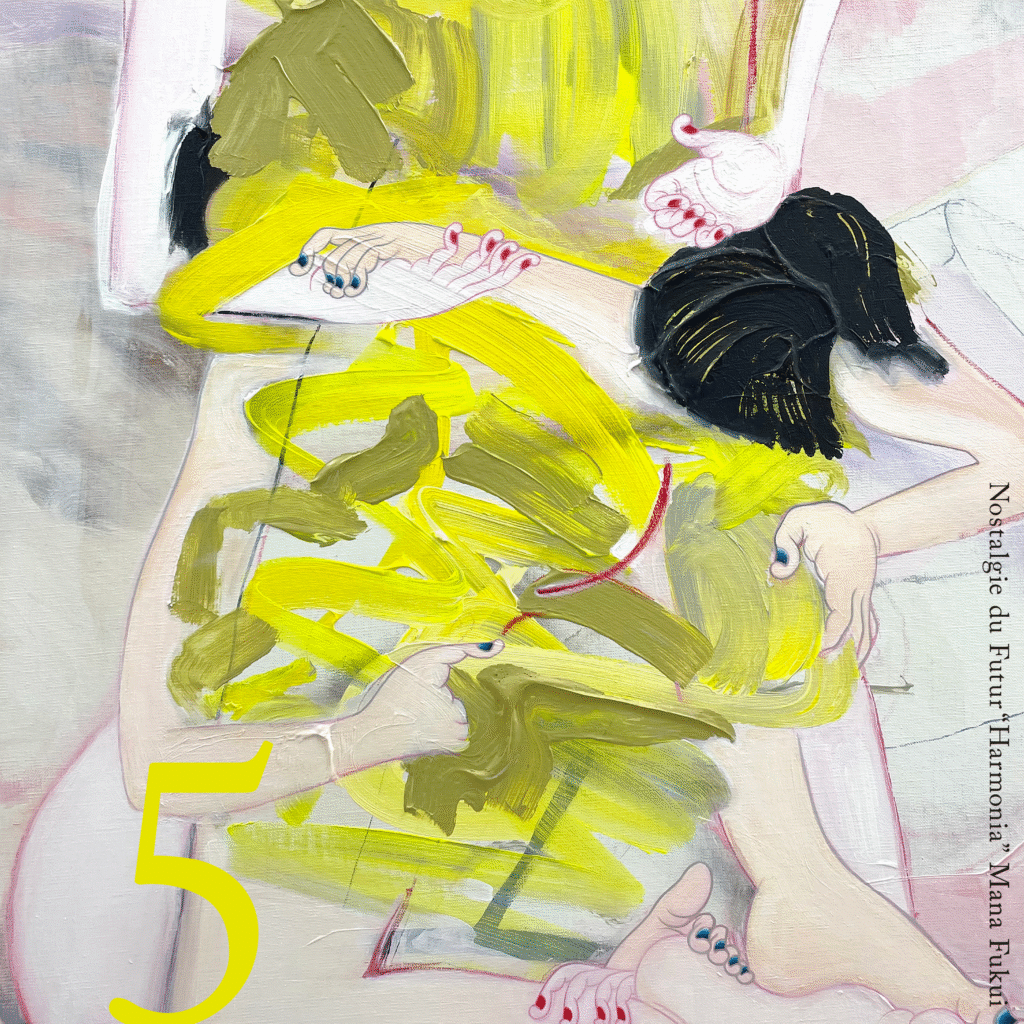
Track List
| 1 | シックス・ピアノズ | スティーブ・ライヒ |
| 2 | ヴォカリーズ(久松義恭 編曲) | セルゲイ・ラフマニノフ |
| 3 | アヴェ・ヴェルム・コルプス(フランツ・リスト編曲) | ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト |

©Leo Kuroyanagi
福井 真菜
Mana Fukui
(ピアノ)
桐朋学園大学ピアノ科在学中、モスクワにてアサネータ・ガブリーロワ氏に師事。同大学卒業後、パリ17区コンセルヴァトワールピアノ科、伴奏科を満場一致の一等賞で卒業したのち、クラマール地方音楽院にて室内楽、声楽クラスの指導、また、シャラントン音楽院にてピアノ科教授として後進の指導にあたる。
現代音楽にも意欲的に取り組み、現代音楽祭、“Musique de notre temps(私たちの時代の音楽)” に定期的に参加。また、高い初見能力、室内楽の豊富なレパートリーを高く評価され、フランス政府国家音楽家資格試験(DEM)、数々の国際フェスティヴァル、コンクール等で公式伴奏員を務めつつ、パリを拠点にヨーロッパ各地でリサイタル、室内楽を中心に演奏活動を行う。
2015年に帰国後演奏活動を精力的に行い、2018年7月、東京オペラシティにてソロリサイタルを開催し、好評を博す。 2022年より室内楽の豊富な経験と知識を生かし、音楽監督として室内楽シリーズ「ユグドラシル」を開催。「音楽の友」、「芸術現代」等の音楽評論において高い評価を得る。
2025年、NHK主催「バレエの饗宴」にて、東京フィルハーモニー管弦楽団とラヴェルのピアノ協奏曲をNHKホールにて共演し、大きな反響を呼ぶ。
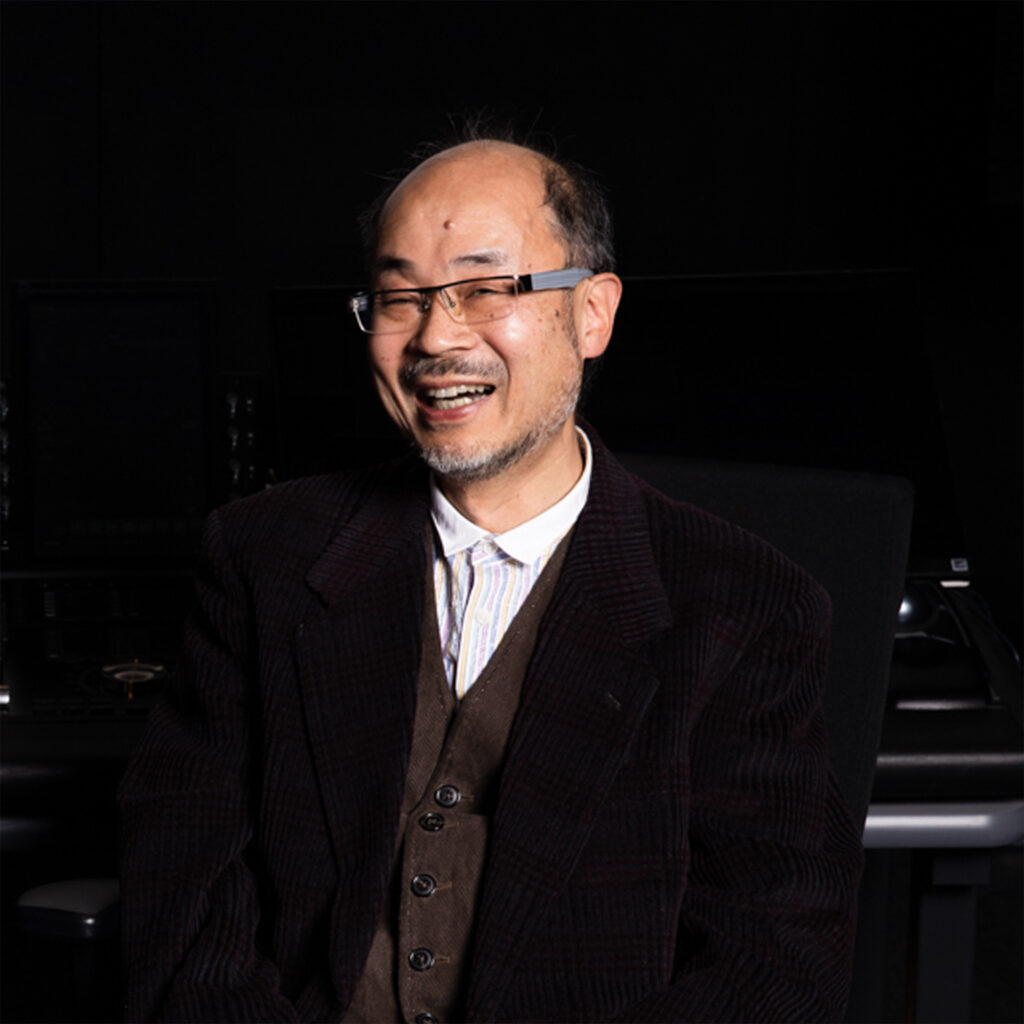
入交 英雄
Hideo Irimajiri
(RME Premium Recordings 音楽監督、エグゼクティブ・プロデューサー)
1956年生まれ。1979年九州芸術工科大学音響設計学、1981年同大学院卒。2013年残響の研究で博士(芸術工学)を取得。1981年(株)毎日放送入社。映像技術部門、音声技術部門、ホール技術部門、ポスプロ部門、マスター部門を歴任。2017年より(株)WOWOWにてイマーシブオーディオの制作技術開発、事業開発。2025年入交イマーシブオーディオ研究所を立ち上げ「ならまちスタジオ」を開設。RME Premium Recordings 音楽監督就任。
1987年、放送業界初となる高校野球サラウンド放送のプロジェクトに関わる。2005年より放送のラウドネス問題研究とARIB委員、民放連委員を通じて規格化に尽力。学生時代より録音活動を行い、特に4ch録音や空間音響について探求を重ね、現在では3Dオーディオ録音の技術開発と共に、精力的な制作や普及活動を行っている。
2021年 冨田勲「源氏物語交響絵巻」(プロ音楽録音賞イマーシブ部門 最優秀賞受賞)
2021年 ボブジェームス「Feel Like Making Live」UHD BD、2024年 MR.BIG 「The BIG Finish Live」UHD BD
また、個人的にも入間次朗の名前で音楽制作活動を行っており、花園高校ラグビーのオープニングテーマやPCゲームのロードス島戦記などを担当。
Recording Information
Recording Dates: January 11–14 and May 16–19, 2024
Recording Location: Yatsugatake Yamabiko Hall, Hokuto City, Yamanashi Prefecture
Credits
General Producer: Seiji Murai (Synthax Japan)
General Music Director & Recording Engineer: Hideo Irimajiri (Synthax Japan)
Piano Performance & Album Curation: Mana Fukui
Video Director: Leo Kuroyanagi (IRISS Inc.)
Artist Relations: Michiko Tatsumi (Muan-sha)
Bösendorfer Tuning: Jun Terunuma
Album Commentary: Yudai Majima (Music Critic)
Web Producer: Yutaka Yuasa(Synthax Japan)
Venue Manager & Marketing Director: Kaori Terasawa (Synthax Japan)
Engineering: Katsutaka Suzuki (Synthax Japan)
Creative Director: Nao Masaki
Artist Paint: Shinichi Kaneko
Special Thanks
Joji Funaki, Sachiko Kawano, Tatsushi Omori,Kanji Murai(Genelec Japan)